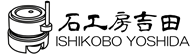石臼全般
玉露を抹茶に
抹茶の材料となる碾茶

碾茶は、日本の伝統的な粉末茶「抹茶の原料」となる茶葉です。
碾茶の製造工程
【被覆栽培】(覆下栽培)
茶葉を収穫する約20日前から遮光して育てることで、苦味を抑え、うま味成分(アミノ酸、特にテアニン)を増やします
覆う素材は、昔ながらの藁(わら)や、現代では黒い遮光ネットが使われます
【蒸し工程】
収穫後すぐに蒸して酸化を防止します。ここまでは煎茶と同様。
【乾燥】
煎茶や玉露のように「揉む」工程は省き、揉まずにそのまま乾燥します
これにより、茶葉は薄く平らな形に仕上がります
【茎や葉脈の除去】(仕上げ)
石臼などで挽く前に、茎や葉脈などを取り除き、柔らかい葉の部分だけを残します
【碾茶の特徴】
見た目:平たくて薄い茶葉、鮮やかな緑色。
味わい:苦味が少なく、うま味が強い。
香り:海苔のような青海苔香(碾茶香)がある。
用途:主に抹茶に加工される。石臼などで微粉末状に挽くことで、茶道用や食品加工用の抹茶が完成します。
【碾茶の文化的価値】
茶道で用いられる抹茶のルーツであり、日本文化や茶の湯と深く結びついています。
海外では入手が難しいため、抹茶と混同されがちですが、**抹茶の前段階にある「原茶」**が碾茶です。
日本の高級茶「玉露(ぎょくろ)」

玉露は、日本茶の中でも最上級のランクに位置する高級茶です。特有のうま味、まろやかさ、甘みがあり、「覆い下(おおいした)茶」と呼ばれる製法で育てられます。
【玉露の栽培方法】(被覆栽培)
茶葉の新芽が出てから約20日前後に遮光ネットで被覆します。
日光を遮ることで、光合成を抑え、渋み成分(カテキン)を減らし、**うま味成分(テアニン)**を増やします。
被覆方法には「本覆い(昔ながらの藁を使う方法)」と「簡易覆い(黒いネットを使用)」があります。
【[玉露の製造工程】
手摘みまたは機械摘み
【蒸し工程】(酸化防止)
揉み工程(茶葉に形を与える)
【乾燥工程】
火入れと仕上げ(風味を調整)
茶葉は針のように細く丸まった形状で、美しい深緑色をしています。
【玉露の味・香りの特徴】
味:とろみのあるまろやかな味わい、甘みが強く、苦味は非常に少ない。
香り:特有の「覆い香(おおいか)」と呼ばれる、海苔に似た上品な香り。
うま味:アミノ酸(特にテアニン)が豊富で、煎茶よりもはるかにうま味が強い。
玉露(ぎょくろ)と碾茶(てんちゃ)は、どちらも高級な日本茶
どちらも高級な日本茶ですが、仕上げの工程に違いがあります。
【共通点】
どちらも新芽を日光を遮って育てる被覆栽培(覆下栽培)で栽培される。
うま味成分(テアニン)を多く含み、苦みが少ない。
高級茶として扱われる。
【違い】
加工行程で[碾茶]揉まない、[玉露]揉む
茶葉の形状[碾茶]薄く広がっている、[玉露]棒状に丸まっている
【碾茶の特徴】
被覆期間:玉露と同じく20日程度。
製造工程で揉まず、そのまま乾燥させる。
主に抹茶の原料として使用される。
茶葉は薄く広がった状態。
粉末にして抹茶にすると、抹茶特有の濃厚な風味と色合いが出る。
【玉露の特徴】
被覆期間:およそ20日程度。
製造工程で揉む(茶葉を形作る)。
一般的に急須で淹れて飲むための茶葉。
茶葉は針のように細長く丸まった形状。
味わいは非常にまろやかでうま味が強く、香りも豊か。
[玉露]を[碾茶]のように挽き[抹茶]にする
[玉露]と[碾茶]は最終段階の仕上げで揉むか揉まないかで茶葉の形状が違いますが
栽培方法は同じなので、細かく挽くとどちらも抹茶になります。
私の制作している抹茶臼は碾茶の薄い茶葉をストレスなく挽く事が出来るように設計しています。
碾茶を挽く場合は上臼の穴に必要量の茶葉を入れて、あとは上臼を回し続ける事で抹茶になりますが、
同じ方法で玉露を挽くと、石臼内部への茶葉の供給量が多すぎるのが原因で非常に粗く挽けてしまいます。
解決方法は玉露の場合でも、石臼内部への茶葉の供給量を少なく調整する事で抹茶にする事が可能になります。
必要量を一度に穴に入れるのではなく上臼の皿の部分に置き、左手で少量いれて上臼を数回まわし、また少量入れて数回まわす作業を繰り返します
出てくる粉の状態を確認しながら上臼を回している右手の感触と茶葉の挽けている音で判断しながら挽き続けます。
[玉露]を[抹茶]にする
[玉露]を[碾茶]の挽き方で挽く
[玉露]を[抹茶]にする事はできます
入手しにくい碾茶ではなく、比較的入手が容易な玉露を抹茶にする方法は 有効な手段だと思います。 海外では特に碾茶の入手は困難なために、この方法をお勧めします。